こんにちは、お坊さんブロガーのへんも(@henmority)です。
家を建てる・車を買う・結婚する・・・など、何か大きなライフイベントにふと気になるのが六曜ですよね。
仏滅にこんなことやってもいいの?
赤口に納車してもいいの?
何かと気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では六曜は気にする必要があるのか?を解説していきます!
タップできるもくじ
六曜とは
中国ではじまった暦のルールで6種類の曜日を指す言葉です。
- 先勝(せんしょう・さきがち)
- 友引(ともびき)
- 先負(せんぷ・さきまけ)
- 仏滅(ぶつめつ)
- 大安(たいあん)
- 赤口(しゃっこう)
この6つの曜日は月の動きを基準にする「旧暦(太陰暦)」をもとにルールが決められています。
六曜のルール
まず、旧暦の1月1日は先勝からはじまります。
その後、六曜の順番通りに曜日が進んでいきます。
- 1月1日(先勝)
- 1月2日(友引)
- 1月3日(先負)
- 1月4日(仏滅)
- 1月5日(大安)
- 1月6日(赤口)
- 1月7日(先勝)
このように進んでいき、月末になるとそこで一旦ストップとなります。
2月になると六曜が1月とはひとつズレて2月1日は友引からスタートします。
- 2月1日(友引)
- 2月2日(先負)
- 2月3日(仏滅)
- 2月4日(大安)
- 2月5日(赤口)
- 2月6日(先勝)
- 2月7日(友引)
というようになります。
まとめると六曜のルールは以下のようになります。
- 1月・7月の1日は先勝から
- 2月・8月の1日は友引から
- 3月・9月の1日は先負から
- 4月・10月の1日は仏滅から
- 5月・11月の1日は大安から
- 6月・12月の1日は赤口から
カンタンにいうと、六曜はただの暦のルールです。
現在月曜・火曜・水曜・・・と使っている七曜と同じようなものですね。
六曜は旧暦を基準にして決められています。
ですので、現在の太陽暦の暦と重ねたときに変則的で不思議なルールに見えてしまうんですよね。
伝統的な古い風習ですし、六曜を仏教と関係するものと考えている方も多いのですが、実は仏教と六曜はまったく関係がありません。
じゃあ神道に関係あるものなのか?というと、それも関係ないんです。
中国の陰陽道で使われていた暦が鎌倉から室町時代に日本に入ってきたといわれていますが、どうやって始まったのかもわかっていないという謎の風習なのです。
六曜の詳細
では六曜のひとつひとつを見ていきましょう。
先勝
先勝は「せんしょう」「せんかち」「さきがち」「さきかち」などと読まれます。
「先んずれば即ち勝つ」という意味で、何事も急いでちゃっちゃとやるのが良いとされます。
午前中がツイてて、午後はよくないらしいです。
友引
友引は「ともびき」と読みます。
「凶事に友を引く」と言われますね。
この日に葬式をすると「友を引く」と言われることがあり、縁起が悪いという理由で火葬場がしまっている地域が多くあります。
慶び事は、友にもお裾分けということで結婚式などを友引にされる方も多いですね。
先負
先負は「せんぶ」「せんぷ」「せんまけ」「さきまけ」などと読まれます。
「先んずれば即ち負ける」の意味で午前中の運が悪くて、午後がツイてる日だそうです。
仏滅
仏滅は「ぶつめつ」と読みます。
「仏も滅するような大凶日」の意味で、六曜の中で最も凶の日(赤口が1番悪いという人も)、結婚式などの慶事を敬遠する方もいますね。
一日中ツイてない日というのが通説ですが、人によっては午後は大丈夫とする説もあります。
大安
大安は「たいあん」と読みます。
「大いに安し」という意味で、六曜の中で最も良い日とされます。
何事においても吉、成功しないことはない日とされ、特に結婚式は大安の日に行われることが多いですね。
赤口
赤口は「しゃっこう」「しゃっく」「じゃっく」「じゃっこう」「せきぐち」などと読まれます。
陰陽道の「赤舌日」という凶日に由来するそうです。
午前11時ごろから午後1時ごろのみツイてて、それ以外はよくないとされています。
この日は「赤」という字が付くため血を連想させ、火の元、刃物を扱う人は特に気をつけなければいけないそうです。
仏滅よりもツイてない日という説も。
六曜に振り回されるなんてくだらない
ここまで六曜の詳細を書いてきましたが・・・正直書いてて馬鹿らしくなってきました。
声を大にして一言言わせてもらおう。

六曜によって良い日だ悪い日だなんて…
そんなもん関係あるかー!!
六曜は特徴的で何か意味のありそうな漢字表記のせいか、日の善し悪しという謎の風習を生み出しました。
本当は何の意味もないただの暦なんですけどね。
普段生活している時はまったく気にもしていないのに、なぜか特別なイベントの時だけ気になる人が多いんですよね。
その証拠に、この記事を読んでいる人の99%の人は今日の六曜は何なのかわからないことでしょう。
でも、結婚式や葬儀などの冠婚葬祭、車の納車、家を建てる、宝くじを買う、など何かちょっと特別なイベントになると急に六曜が気になるのですから人間は不思議な生き物です。
何か良さそう、もしくは、何か良くなさそう、と大事な出来事の日程を六曜を基準にして決めることがありますが、実は六曜はまったくあてにならないものなんですよ。
六曜はもともと違う漢字が使われていた
六曜に使われている漢字や表記は時代とともに変化しています。
諸説ありますが、もともとは現在使われている漢字とは違った言葉でした。
| 古い表記 | 現代の表記 |
|---|---|
| 即吉 | 先勝 |
| 共引 | 友引 |
| 周吉 | 先負 |
| 虚亡・物滅 | 仏滅 |
| 泰安 | 大安 |
| 赤口 | 赤口 |
こんな風に赤口以外は全てもとの漢字と言葉が変わっているんですね。
友引は共引
もともと友引は共引と書かれていて、「共に引き分け」という意味です。
「共引」は先勝と先負のあいだにあることからも引き分けというのは納得できますよね。
それがどういうわけか「友」という漢字に変換されて「友引」と書かれるようになり、後付けで友を引く日だなんて言い出したのです。
たったこれだけの、こんなくだらない理由で
「友引に葬式して、なんか縁起の悪いことがあったらダメだ!」
というようになったのです。
地域によっては友引が火葬場の定休日になっていて閉まっているところも多いですよね。
だいたい、友を引く日に葬儀をしたら「亡くなった方のせいでまた別の死者がでる」なんて失礼極まりないことだと思いませんか?
まぁ365日24時間体制のお坊さん的には、この日は葬儀が入らないという「予定を確保できる日」があるのは正直言って助かります。
葬儀が入らないことが確約されていれば、お坊さんどうしの勉強会や会議などはその日に設定できますからね。
仏滅は物滅
仏滅も仏が滅する日だから悪い日だ!という説は、漢字の意味から後付けされたものです。
もともとは物が滅する「物滅」と書かれていましたが、字が変換されて「仏滅」となりました。
この漢字変換には暦の上での数学的な偶然も仏滅という字に変換される理由があったのだと推測されます。
仏教の開祖であるお釈迦様が亡くなられた日は旧暦の2月15日です。
2月は友引からはじまりますので友引→先負→仏滅・・・と進んでいくと2月15日は100%仏滅にあたります。
これはたまたまです。
ですが、「字面」と「日にち」という偶然も重なって、「仏が滅する」なんて意味が後付けされたのでしょう。
なんで特別な日だけ六曜を信じるの??
人はなぜ特別な日だけ六曜が気になってしょうがないのでしょうか?
物事は極端にするとその本質がよくわかりますので、どうせなら六曜をめちゃくちゃ意識しながら生活してみたらどうなるでしょうか。
六曜を気にする生活
六曜を普段から気にしながら生活すると、以下のようなことを言い出しても不思議じゃないんですよね。
先負なんで、午前は仕事を休んで午後から出勤します!
今日の合コンは中止にしたほうがいいぜ・・・
なんせ仏滅だからな・・・。
赤口なので、今日は火を使う料理はやりません!
全部生で食べる!
こんな話が通用するのか?という話です。
会社にこんな人がいたら、どう考えても変なヤツって感じになりますよね。
日がいい、悪いなんてことが行動指針になるなんて、あまりに馬鹿げていると思いませんか?
六曜は気にしなくていい
ここまで言って、頭で理解できても納得がいかないのが迷信の根深さです。
浄土真宗の開祖、親鸞聖人は和讃の中でおっしゃっています。
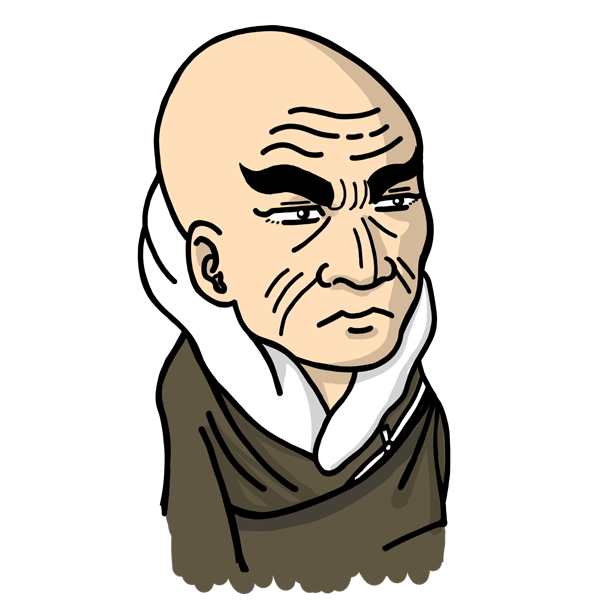
かなしきかなや道俗の 良時吉日えらばしめ 天神地祇をあがめつつ ト占祭祀つとめとす
ちょっと言葉が難しいので、唯円くんに訳してもらいましょう。
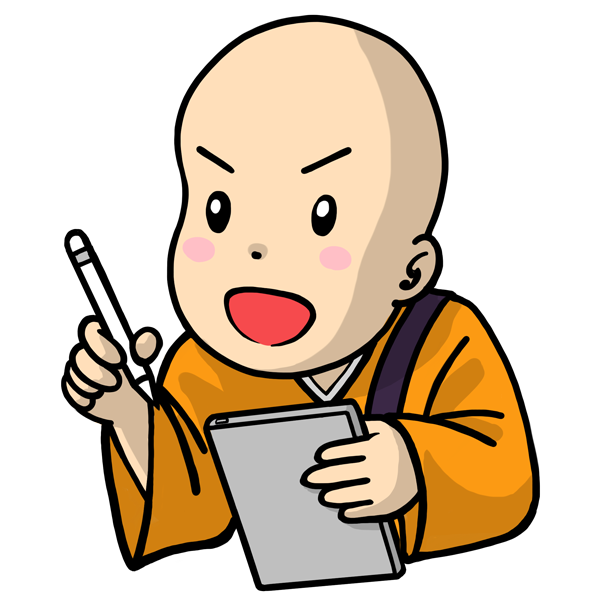
一般の人たちも僧侶も、日がいいとか悪いとかめっちゃ言うのよね。
それであちこちの天の神や地の神をおまつりしたり、あてにもならん占いや祈りごとばっかりして、本当に考えないといけない肝心なことが抜け落ちている、つらたん・・・(´・ω・` )
って事ですね!
この和讃が読まれたのは今から750年ほど前のこと。
750年も時を経ているのに、現代でも同じように根拠もない迷信に多くの人が振り回されているんだから、いかに人類は成長していないかということですね。
それだけ人間の迷信に対する不安感は根深いということなんでしょう。
本当に六曜が力を持っているとしたら、車の納車日を大安にすれば事故は起こらないはず。
大安に結婚式をして夫婦生活がうまくいくなら結婚した人の3分の1も離婚しないでしょう。
まぁ離婚が不幸かどうかは人によるので、よくないことかどうかはわかりませんが。
結婚式場は大安や友引の土日から予約が埋まりますので、なんだかんだいまだに強い影響力があるということですね。
はっきりいいます。
仏滅に結婚式したからといって何も悪いことなんて起こりませんよ。
むしろそういう合理的な判断をできる相手と結婚する方が、夫婦生活もうまくいくんじゃないかとさえ思います。
今の暦で言い換えたら、「月曜日に結婚式をするのは縁起悪い、火曜日にしよう!」なんて言ってるようなものです。
要するに、六曜に振り回される精神性とは何かというと、何かうまくいかなかった時に自分の責任にしたくないということなんですよね。
うまくいかないこと、思い通りにならないことが人生には起こります。
それをいかに受け止め、自分の人生の歩みとしていけるかが人生の醍醐味ではないでしょうか。
友引に恋人にフラれることもあるし、大安に交通事故にあう人もいます。
六曜のような根拠のない迷信を人生の支えとするのではなく、自分の人生に責任をもって生き、理性的な判断をするということが重要です。
六曜なんて気にしなくていいんです。
何が本質なのかを見極める目を養って、理性的に生きたいものですね。
その一日を良くするのも悪くするのも、あなた自身の生き方ですよ。
※途中ででてきた親鸞聖人と唯円さんのナイスコンビがお届けするLINEでわかる歎異抄シリーズも人気です!

















