こんにちは、善照寺の住職(@henmority)です。
僧侶と一般の方で、意味の認識がまったく違う言葉がひとつあります。
それが「他力本願」という言葉です。
誤用があまりにも浸透してしまって、本来の意味を知っている方がほとんどいなくなってしまいました。
言葉の意味は時代とともに変わっていくのは世の常ですから、その流れを変えることはもはやできないかもしれません。
しかし!
一応僧侶として一言言っておきたいわけです。
おそらくほとんどの人が知らない「他力本願」の本来の意味。
この機会にご一読ください!
タップできるもくじ
なぜ『他力本願=他人任せ』と誤解されるのか?
「他力本願」という言葉を耳にしたとき、どんなイメージを持ちますか?
日常耳にする使われ方だと、「自分で努力せずに、他人の力に頼って楽をしようとすること」だと思っているのではないでしょうか。
でも実は本来の意味から大きく変化してしまった間違った使い方なのです。
「他力本願」という言葉は本来、仏教、特に浄土真宗の根幹をなす大切な教えを指しています。
ところが、今ではすっかり「人任せ」「棚ぼた狙い」といった意味で広まってしまいました。
なぜ、こんなにも意味がねじ曲がってしまったのでしょうか?
理由のひとつはやはり「言葉の字面」と「語感」でしょう。
他力本願は自力で頑張るの反対語?
勉強でもスポーツでも、自分の力で努力することを「自力で頑張る」って言いますもんね。
この対義語として「他力」と考えるのは自然な感覚だと思います。
ですから、「他力」は自力ではないものとして他人の力とか、まわりの環境の力や運のようなものという印象になるのも無理はありません。
そして後ろの「本願」という字面には「自分の本当の願い」とか「めっちゃ願ってる感」がありますもんね。
この2つの他力と本願の意味が組み合わさることで、他人の力で願いを叶えるという印象になってしまったのです。

自分の努力で結果を出すんじゃなく、周りの誰かが運良く助けてくれたり、環境が勝手に整って自分の目標が達成されて欲しいという、まさに人事を尽くさず天命を待つ感じですよね。
誤用されがちな「他力本願」の意味は、一般的にはこのように捉えられています。
- 自分の力じゃない力で自分の目的が達成されること
- 他人に依存しなりゆきにまかせること
- なんかわからないけど、楽をしてうまくいくこと
でも本来、他力本願という言葉はこのような意味ではありません。
むしろ、仏教の視点から見ると、とても積極的で主体的な生き方を表す言葉なのです。
仏教における他力本願の教え
まず「他力」という言葉について考えて見ましょう。
「他力」という言葉はもともと仏教の中で使われる言葉なのです。
自力と他力
仏教は悟りの世界をめざし仏になることを目標とする教えです。
このとき、自分の修行によって悟りに向かっていくことを「自力」といいます。
この「自力」に対して、「仏」の力によって悟りに到達することを「他力」と言います。
親鸞聖人は明確に「他力」とは何かということをおっしゃっています。
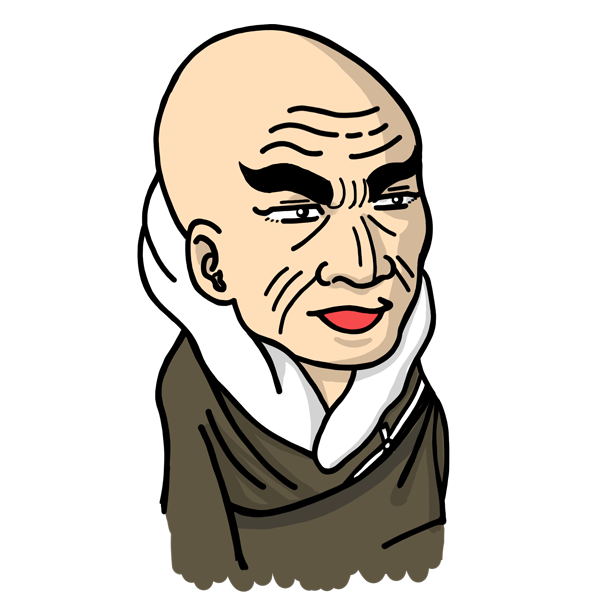
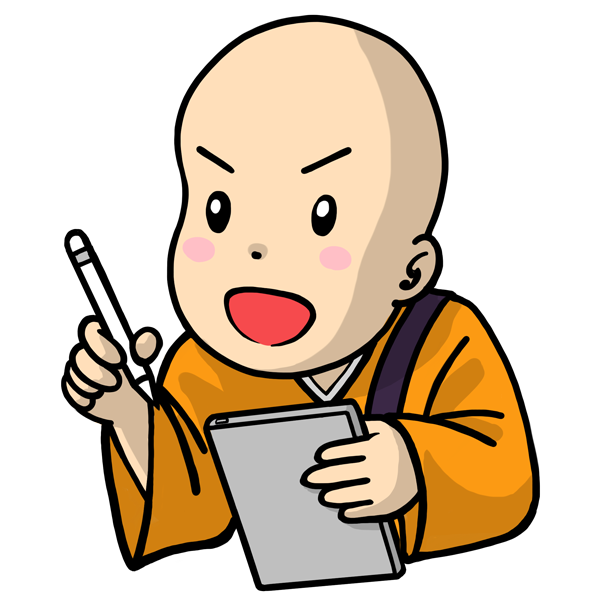
他力と言う言葉の意味は、他人の力でも、自然の力でも、運でもありません。
阿弥陀仏の力のはたらきを他力というのです。
本願は阿弥陀仏の「願い」であり「はたらき」
本願は私が願っているのではなくて、阿弥陀仏の願いのことを指します。
阿弥陀仏のはたらきとは何かというと、欲にまみれた人間をすべて浄土という仏の世界にうまれさせ、仏にするはたらきのことです。
・・・・よくわかりませんね。
もう少しわかりやすい表現・現代的な感覚に書き換えるならば、浄土の教えを聞くことで自らの姿をかえりみて、生き方を考えようということになります。
浄土の世界観というのは生きとし生けるものが平等に、隔たり無く、優劣も無く、傷つけ合わず、違いを認め合って尊重しあって共存する世界観です。
その世界観を人生の「芯」に据え、念仏をしながら生きる生き方が「他力本願」を聞いていく生き方です。

という阿弥陀仏の「願い」というのが他力本願であって、決して「私の願いが叶うこと」ではないんですよ。
阿弥陀仏をたのむって言い方もちょっと難しい
一般知識として、「浄土真宗は念仏をすれば阿弥陀仏の力で救われる」宗教というイメージだと思います。
このことを「阿弥陀仏をたのむ」っていう言い方をするんですが、この言い方も誤用を生み出す一因になっている気がします。
通常たのむというと「お願いする」という意味です。
お使いをたのむとか、講演をたのむなどですね。
ですから阿弥陀仏にたのむ、というのもこちらから何かお願いをする感じの言葉として受け取るのも無理はないのかもしれません。
ですが、ここでいう阿弥陀仏をたのむというのは漢字で書くと「頼む」ではなく「憑む(たのむ)」と書きます。
これは依頼するという意味ではなく「よりどころとする」という意味で使われる言葉なのです。
ですから、阿弥陀仏をたのむというのは先にも書いたとおり他力本願の教えをよりどころとするということ。
「教え」をよりどころとすると、生き方に「芯」ができます。
そういう何を大事に生きるのかという生き方の「芯」が整うと、厄年や六曜みたいな論理として破綻している謎の迷信なんかに振り回されることがなくなります。
本来的な意味で言葉を使うなら「他力本願」を聞いていく生き方こそ、浄土真宗の門徒としてあるべき姿なのです。
このことが理解できらば、他力本願という言葉が決して「他人任せの無責任な生き方」ではなく、むしろ主体的に生きるための指針であることがわかるのではないでしょうか。
他力本願まとめ
メディアをはじめ、世間のほとんどの人が「人任せ、なりゆきまかせ」という意味で使っているため、「他力本願」という言葉はなかなか本当の意味を知ってもらえません。
たしかに誤用とはいえ、他力本願以外の言い方で「自分では何もやらず、人任せやなりゆきまかせにすること」を指す言葉をぼくは知りません。
そういう誤用で使われている意味を他に言い表す言葉が無いことや字面の雰囲気もあって、この「他力本願」という言葉は間違った使い方が広まったのだと推測されます。
ですから、今さら他力本願の使い方は誤用だ!
・・・といくら言ったところでどうにもならないかもしれませんが、このブログを読んだ方には、このことだけは覚えていて欲しいのです。
- 他力本願という言葉は浄土真宗の教えの根幹であること
- 他人任せにするという意味は誤用であること

とか

というような言い方や書き方はしないほうが賢明だと思われます。
浄土真宗の教えを大事に生きておられる方にとっては大事なものをけなされた感じになりますし、大勢の前でそういう使い方をすると自ら無知をひけらかすことになります。
言葉の意味は時代の中で変わっていくものとは言いますが、この言葉は浄土真宗の教えを聞く者にとってはとても大切な言葉です。
冥福を祈るという言葉もそうですが、言葉の意味を理解して適切な使用をした方がいい言葉のひとつなのです。















